「減価償却の計算は、毎年面倒だし、できればやりたくないんだけど……」
「買ったものは、買った年の経費にしたい!」
こんなふうに思われた経験、誰しもおありではないでしょうか。
減価償却の計算をしないでいい、そんな便利な方法はあるのでしょうか。
当記事では、一定額までの減価償却資産であれば、減価償却の計算をしないで
購入した年の必要経費にできる特例【少額減価償却資産の必要経費算入の特例】
について、わかりやすく解説していきます!
30万円未満の減価償却資産は購入年の必要経費にできる(要件あり)
結論からお伝えすると、
「30万円未満の」減価償却資産は、減価償却しないで、購入した年の必要経費にできる
という制度があります。
しかしながら、この制度はあくまで特例として認められるもの。
次の項目では、この特例制度を使うための要件をくわしく見ていきましょう!
ポイント 減価償却について
減価償却制度の原則(基本的な考え方)は、「使用可能期間が1年以上」かつ「取得価額が10万円以上」で、使用するにつれて価値が減っていくものは、その年に全額を必要経費にするのではなく、使用可能期間に分割して経費を計上(減価償却)する、というもの。
計算方法などは、こちらの記事(個人事業の減価償却資産とは?減価償却で必要経費に計上する方法を解説【定額法】)で解説しています。ぜひあわせてチェックしてみてくださいね。
特例制度の適用要件とは?
ここからは、30万円未満の減価償却資産を取得したときに、その年の必要経費に取得価格を全額計上できる(減価償却しない)特例を適用するための要件を、順に確認していきます。
根拠法令等:租税特別措置法28条の2、租税特別措置法施行令18条の5
要件1 青色申告をしていること
まず、その年に青色申告をしていることが要件とされています。
したがって、白色申告のかたは使うことができません。
この特例のほかにも、青色申告にはいろいろなメリットがありますので、個人でビジネスをするかたは、お早めに青色申告の承認申請書を提出しておくのがおすすめです。
青色申告の承認申請の方法やメリットについては、以下の記事でくわしく解説しています。
よかったら参考にしてみてくださいね。

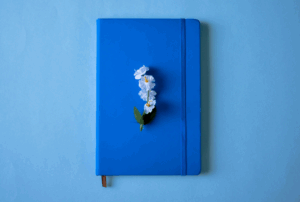
なお、青色申告をしている個人のかたであっても、常時雇用する従業員が500人を超えていると、この特例を適用できないこととされています。
(個人事業で500人以上を雇用するというのは、とても珍しいケースだと思いますが……)
要件2 特例を使える減価償却資産の合計は各年300万円まで
この特例は、ひとつの資産ごとに、その取得価格が30万円未満かどうかを判定します。
たとえば、ある年に25万円のパソコンを3台購入したとき。
この場合は、合計金額75万円をその年の必要経費に計上できます。
ここで注意したいのが、この合計金額には制限があり、300万円が上限とされていること。
たとえば、25万円のパソコンを15台購入すると、合計金額は375万円ですが、
この特例を使って全額をその年の必要経費に計上できるのは、300万円まで(つまり、12台分)。
残りの75万円(3台)は、原則どおりの減価償却をしなくてはなりません。
また、年の途中で開業や廃業をして、事業をしていなかった期間があるときは、その分の上限額が少なくなることにも注意が必要。
たとえば7月に開業した場合、開業した年の稼働期間は6か月なので、この年の上限は300万円に12分の6を掛けた金額、すわなち150万円になります。
要件3 青色申告決算書に特例の適用について記載が必要
この特例を使うときは、確定申告の際に、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄(3ページ目)に所定の事項を記載することになっています。
ポイントは、摘要欄に「措法28の2」と記載すること。
あわせて、取得年、金額なども記載が必要です。
国税庁のHP(こちら)に記載例が掲載されていますので、確認してみてくださいね。
少額減価償却資産の特例を適用するメリットは?
ここまで、特例制度の内容を解説してきました。
次に、この特例を使うことで得られるメリットを確認しておきましょう!
メリット1 購入した年の節税効果
減価償却しないで、購入した年に全額を必要経費に計上できるということは、購入した年の事業の所得を減らすことができるということ。
したがって、その年の所得税、住民税などの税金を減少させる効果があります。
ただし、その裏返しとして、翌年以後の必要経費に計上できる金額は少なくなることには注意が必要です。
メリット2 事務的コストの削減効果
減価償却の計算をしなくていい、というのは、経理事務に手間をかけたくない事業者のかたにとっては大きなメリットといえます。
面倒な計算をしないで簡単に終わらせられるなら、それに越したことはないですよね!
注意すべき点は? 減価償却したほうが有利な場合も
メリットがある一方で、デメリットが発生するケースも。
最後に、押さえておきたい注意点を確認しておきましょう。
ポイントは、特例を使わずに減価償却の計算をしたほうが、税額の面で最終的には有利になるケースがあるということ。
この特例は、あくまで、減価償却で分割して計上するはずだった金額を、減価償却ではなく、購入した年にまとめて計上するというもの。
つまり、最終的に計上できる必要経費の金額は同じです。
購入した年に全額を必要経費に計上できるということは、翌年以降に、本来であれば計上できるはずだった減価償却費を計上できないということ。
税額の計算においては、所得が多くなる年、すなわち、所得税の適用税率が高くなる年に必要経費を計上するほうが、トータルでみたときに発生する税額は少なくなります。
たとえば、開業初期に資産を購入し、その年はまだ収入が少ないけれど、その翌年以後は事業が軌道にのって税額が大きくなりそうだ、と予想しているとき。
この場合は、特例を使わず、通常の減価償却の計算をして翌年以後にも減価償却費を計上できるようにしたほうが、最終的に支払う税金の額は抑えられるかもしれません。
しかしながら、資金繰りなどの観点から、最終的な税額の合計額よりも当面発生する税額を減らすことのほうを優先すべきというケースも、もちろんあります。
まとめ
いかがでしたか?
30万円未満の減価償却資産は、減価償却の計算をせずに、取得した年に必要経費に計上することができます。
しかし、それには要件があり、まずは要件をみたしているかどうかを確認しなければなりません。
また、ビジネスの状況によっては、あえて特例を使わず減価償却をしたほうが有利なケースもあります。
後になってから「あのとき、こうすればよかった……!」と感じることがないように、ご自身の状況を踏まえて総合的に検討し、納得感のある選択ができるといいですね。
当記事が、みなさまのお役にたてるとうれしく思います。







コメント