事業をおこなうにあたって、収入を得るために様々な支出が発生します。
通常、そうした支出は、支払をした年の経費として、その年の収入から差し引きます。
けれど、支払をした年に、全額を経費に計上できない場合があるのをご存じでしょうか。
「何年も使えて、金額の大きいもの」
かつ、
「年数の経過につれて価値が減っていくもの」
こうしたものは、減価償却資産といい、
購入した年に全額を必要経費に計上するのではなく、その年から数年にわたって分割して計上しなくてはなりません。
誤って購入時に全額を計上してしまうと、税務署から経費の過大計上を指摘されるリスクも。
減価償却の制度を正しく理解して、税務のリスクを減らしましょう!
減価償却資産とは
どういったものが、購入した年に全額を必要経費に算入できない「減価償却資産」とされているのでしょうか。
答えは、「耐用年数(使用可能期間)が1年以上」かつ「取得価額(購入価格)が10万円以上」で、使用年数の経過につれて価値が減っていくもの。
逆に言うと、「使用可能期間が1年未満」または「取得価額が10万円未満」のどちらかに当てはまるものは、減価償却の計算は不要。全額を購入した年の必要経費に計上できます。
たとえば、事業用にパソコンを購入した場合を考えてみましょう。
パソコンの耐用年数は1年以上なので、
・ 取得金額が10万円未満であれば、購入時に全額を必要経費に。
・ 取得金額が10万円以上であれば、耐用年数にわたり分割して必要経費に計上
することとなります。
※ 青色申告をしているかたは、30万円未満であれば全額を購入した年に必要経費に算入できる特例があります。
減価償却費の計算の方法とは(定額法)
次に、各年に計上する必要経費(減価償却費といいます)の計算の方法を見ていきます。
ここでは、個人事業の法定の計算方法である「定額法」を解説します。
(税務署に届出書を提出することで「定率法」による計算をすることも認められています)
定額法とは、その名のとおり、毎年一定の額を経費に計上する方法。
さっそく、計算の手順を順に確認していきましょう!
手順1 耐用年数を調べる
耐用年数とは、簡単に言えば、おおよそ何年のあいだ使えそうかということ。
この「耐用年数」にわたって、分割して必要経費に計上します。
ただし、ひとりひとりが自由に年数を見積もると、人によって想定に差異がでたり、恣意的に年数を増減させたりすることができるので、
その年数は、資産の種類ごとに法律で定められた年数を用いることになっています。
法律で定められた耐用年数は、国税庁のHP(こちら)に掲載されています。
たとえば、上で例としたパソコンの耐用年数は「4年」です。
手順2 償却率を調べる
次に、耐用年数に応じた「償却率」を調べます。
償却率も、国税庁のHP(こちら)に掲載されていますので、確認してみましょう。
たとえば、耐用年数が「4年」の場合の定額法の償却率は「0.250」です。
手順3 減価償却費を計算する
最後に、毎年の必要経費に計上する金額(減価償却費といいます)を計算します。
計算式は、
「取得価額」×「償却率」。
たとえば、30万円のパソコンの場合、毎年の減価償却費は
30万円(取得価額)×0.250(耐用年数4年の償却率)=7万5千円
となります。
ただし、年の途中で購入したものは、使用した月数分のみを計上することに注意が必要。
たとえば、9月に購入して事業に使い始めた場合、その年に使用した月数は9~12月の4か月なので
上記の7万5千円に「12分の4」をかけて「2万5千円」が、購入1年目に必要経費に計上する金額となります。
次年度以後は毎年7万5千円を計上し、最後の年(5年目)は残りの額を計上します。
まとめると、上記の「耐用年数4年のパソコンを30万円で9月に購入」のケースでは、次のように取得価額30万円を5年間にわたり分割して、必要経費に計上することになります。
| 購入1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
| 必要経費に 計上する額 | 25,000円 ※4ヶ月使用 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 49,999円※ |
※ 資産を処分するまでは1円を残存価格として残しておくため。
この1円は、処分した年の必要経費に計上します。
まとめ
いかがでしたか?
当記事では、減価償却資産の内容と減価償却費の計算方法について解説しました。
最初は難しく感じられるかもしれませんが、慣れれば意外と簡単に計算できるのではないでしょうか。
いろいろな資産を当てはめて実際に計算してみると、より理解しやすいと思います。
事業で購入したもののなかに、減価償却の計算をすべきものがないか、一度チェックしてみてくださいね。


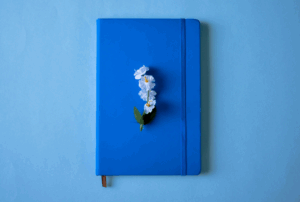






コメント